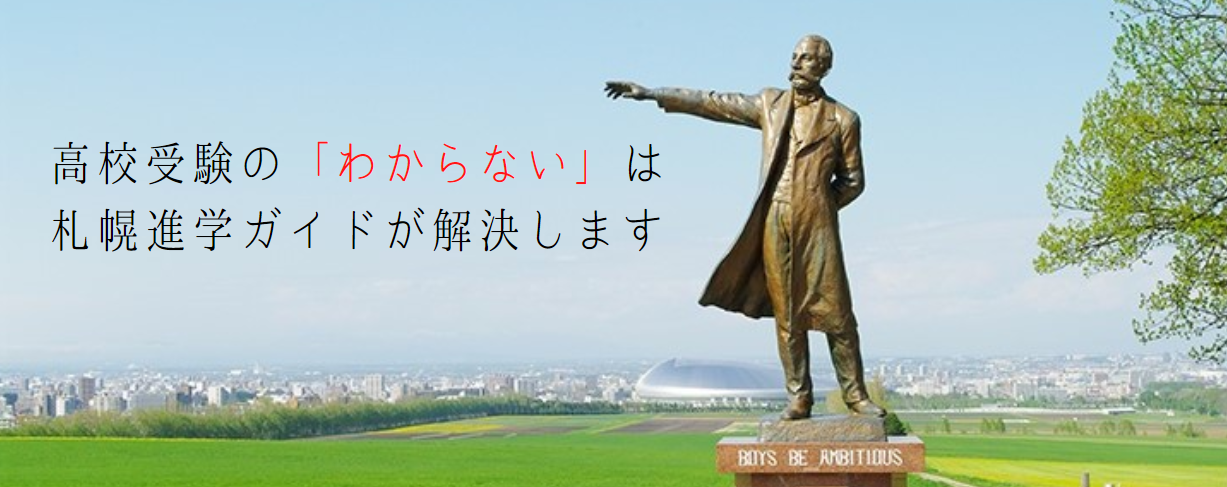【北海道】高校入試のしくみをわかりやすくお伝えします。
札幌進学ガイドをご覧いただきましてありがとうございます。
当サイトは、小中学生と保護者の方に、さらに有益な教育情報を伝えるために2026年4月にリニューアル致します。只今準備中です。どうぞご期待ください!
さて、このページでは「北海道の高校入試のしくみ」についてお伝えします。
北海道の高校入試では、入試当日の得点である「当日点」と中学校から提出される「内申点」の両方を考慮して合否が決められます。
それぞれについて説明します。
目次
1.当日点について
2.内申点について
3.内申点の計算方法
4.内申点のランク
5.合否判定の手順
1.当日点について
「当日点」とは、入学試験当日の得点のことで「入試点」「学力点」とも言われます。北海道の入学試験には、3つの特徴があります。
【2.内申点について】
「内申点」とは、主要5科目のほか実技教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭科)も含めた9教科の評定を合計して計算したものです。
評定は、1~5までの5段階あり定期テストの結果のほか、授業態度、提出物、小テストや欠席なども含めて総合的に評価されます。
評定は、一般的に期末テスト(年3回~4回)ごとにつきますが、内申の計算に使われるのは学年末のものです。
なお、学年末の評定は3学期の内容だけで決まるのでなく、1・2学期の頑張りも合わせて総合的に評価されます。
つまり、学年末テストだけ頑張るという姿勢ではいけません。
3.【内申点の計算方法】
下の3つの数字を合計したものが内申点になります。
中1の学年末の評定の合計(9教科)×2
中2の学年末の評定の合計(9教科)×2
中3の学年末の評定の合計(9教科)×3
例えば、1・2年生の学年末の通知表がオール3、3年生の学年末がオール4の場合、
計算は下のようになります。
| 中1 |
3×9教科=27 |
| 中2 |
3×9教科=27 |
| 中3 |
4×9強科=36 |
54+54+108=216
この場合、内申点は216点(Eランク)になります。
この計算方法の良さは、3年間真面目に取り組めばそれなりに評価してもらえることと、(3年生の評価が3倍になるので)最後の1年で挽回できる可能性も残されていることです。
ここで、注目すべきことは、主要教科も副教科も同等に計算されること。
副教科は得意、不得意のせいか手を抜きやすい傾向があります。
しかし、数学や英語で評価をあげことと技術家庭科で上げることが同じ結果になるなら、後者のほうが楽だと考える人もいるでしょう。
志望校を決定する頃(3年生の秋)になってから、内申点が足りないことに気づき、「副教科も真面目にしておけばよかった」と後悔する生徒は少なくありません。
大切なことは、1年生から副教科にも手を抜かないということです。
4.【内申点のランク】
内申点は、得点ごとにAからMまでの13ランクに分けられます。
前述したように、入試の合否は「当日点」と「内申点」の両方で判断されるので、中学校の進路指導では「志望校が〇〇高校でしたら、ランクは△で当日は△必要です」という具合に説明を受けます。
ランクの上下も大切ですが、同じランクでも点数が高いほうが評価されます。
◇内申ランクの表
| Aランク |
296点~315点 |
|---|---|
| Bランク | 276点~295点 |
| Cランク | 256点~275点 |
| Dランク |
236点~255点 |
| Eランク | 216点~235点 |
| Fランク | 196点~215点 |
| Gランク |
176点~195点 |
| Hランク | 156点~175点 |
| Iランク | 136点~155点 |
| Jランク | 116点~135点 |
| Kランク |
96点~115点 |
| Lランク | 76点~ 95点 |
| Mランク |
63点~ 75点 |
ランクの影響は大きくて、1つ上がると模試の合格予想が20%もはね上がることもあります。ランクを上げたいならテストの時だけ頑張るのではなく、普段からどの教科を上げたいのかを意識することが大切です。
5.合否判定の手順
合否は「当日点」と「内申点」の両方を考慮し、次のような手順で判定されます。
①内申点と当日点を同等に評価し、定員の70%を選びます。(定員320人の場合:224人)
②当日点を重視して、定員の15%を選びます。(定員320人の場合:48人)
③個人調査票(内申点を含む)を重視して定員の15%を選びます。(定員320人の場合:48人)
◇内申ランク・当日点相関表のイメージ.png)
②と③のどちらを先に判定するかということと、②と③で当日点と内申点をどの程度重視するかということは各高校の判断になります。
それぞれの判断基準は、各学校の紹介ページの「入試情報」に下のような表で書いてあります。
◇判断基準の例
|
*学力検査の |
*個人調査書等を重視 |
*傾斜配点の教科 |
学力検査以外の |
|---|---|---|---|
| 9:1 |
6:4 |
英語(2.0) | なし |
◇判断基準の表の見方
【傾斜配点の例】
英語が90点、他の4教科がそれぞれ70点の場合を考えてみましょう。
(5教科の満点は100点×5=500点です)
◆ 傾斜配点がない場合
すべての教科を同じ重みで計算します。
70点×4教科+90点=370点/500点
◆ 英語に傾斜配点(2.0倍)がある場合
英語の点数を2倍して計算します。
70点×4教科+90点×2=460点
この460点は、英語を2倍にしたため600点満点中の得点です。
(5教科のうち英語だけが2倍=合計満点は600点になります)
500点満点に換算すると、
460 ÷ 600 × 500 = 約383点
◆ 結果の比較
傾斜配点なし英語に2倍の傾斜配点あり
得点(換算後)370点約383点
差ー+13点アップ
◆ まとめ
英語のように得意な教科が傾斜配点の対象になっていると、
同じ実力でも総合点が上がることがあります。
つまり、指定された科目が受験者の得意科目であれば入試で有利になります。